お知らせ
保護中: 【第1章】みずからハードモードな人生を選択してしまった小学生


あかね(ちゃこ)
一級建築士
4人の子どもを持つアラサー建築士です。
26歳で一級建築士資格を取得し、28歳で建築設計事務所を立ち上げました。
そこで様々な出会いがあり、現在は一級建築士を目指す受験生さんたちのサポートのお仕事をしています。
これまでのこと
2016:一級建築士に合格
(子育てしながらの挑戦で大変すぎた)
2019:自分の体験をブログに綴る
(多くの受験生が読みにきてくれる)
2019:受験生サポートを始める
(コメント欄やメールで質問回答から)
2021:本格的なコーチングを開始
(1人ひとりの合格にコミット!)
このサイトでは一級建築士試験の攻略法やコーチングサービスの様子をお伝えしていきます♪
\ SNSはこちらから /

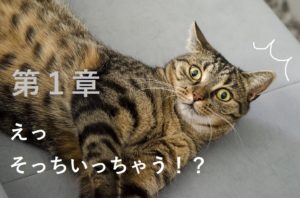
この記事が気に入ったら
フォローしてね!